
覚えておくべき例外 (1) 時制の一致
(前のウェブサイトのブログから再掲載 2021年)
中学や高校で英語を学んだとき、たくさんの文法の基本ルールを覚えたと思います。
基本ルールを覚えるだけで大変ですが、
実際の英文を読んだり聴いたりしたとき、
やっと覚えたはずのルールと違う「例外」に出会い、
とまどいや疑問、驚きを感じた方も多いと思います。
今回はクラスでよく出る疑問・質問の一つ、
「時制の一致の例外」を紹介します。
時制の一致:主節の動詞が過去形の場合に、従属節の動詞の時制が影響を受け変化すること。
(A) A weather forecaster says that heavy snow is expected along the Sea of Japan coast.
(気象予報士は、日本海沿岸に大雪が予想されると言っている)
(B) A weather forecaster said that heavy snow was expected along the Sea of Japan coast.
(気象予報士は、日本海沿岸に大雪が予想されると言った)
(C) A weather forecaster said that heavy snow is expected along the Sea of Japan coast.
(気象予報士は、日本海沿岸に大雪が予想されると言った)
上の3つの英文は、どれも正しい文章です。
(A)は、気象予報士がそう言っているという事実として、主節も言った内容(従属節:that節)も現在形。
(B)は、気象予報士が言ったのが過去なので、時制の一致でthat節が過去形になっている。
(C)は、気象予報士が言ったのは過去だが、内容(大雪が降るという予想)は生きている、すなわち、この文(ニュース)が伝えられている時点で、過去になっていないので、現在形のまま。
(B)の場合、この予報がもう終わったこと・過去のことなのか、これからのことなのか、わからないのに対し、
(C)の場合は、予報が出たのは昨日でも、今日の時点でまだ大雪が降る可能性があるので気をつけないと、と聴いた人は感じる、というわけです。
ニュースではこのように、伝える時点での時間感覚・聴いてる人に臨場感を持って伝えることが大事なので、時制の一致が行われないことが多いのです。
『話した内容が、いまだに真実または有効である場合、時制の一致が行われない』
「不変の真理」や「現在の事実、習慣」「格言」の場合は、時制の一致が行われません。
例)
The teacher said that the earth goes around the sun once a year.
(先生は、地球は1年に1回太陽のまわりをまわると言いました)
先生が言ったのは過去でも、地球が太陽の周りをまわっているというのは事実なので、thatの中は現在形のまま。
高校生の時、必死になって覚えた「時制の一致」は何だったのかと、若干がっかりしてしまいますが、
世の中、「例外がないルールは例外なくない」というのは真理だったり……
あ、これを英訳すると
Coolmint said that there is no rules without exceptions.
(クールミントが言いました。例外のないルールはないと。)時制の一致なし!
続きは『覚えておくべき例外2』へ。
必読!覚えておくべき例外(2) 分詞構文
by クールミント



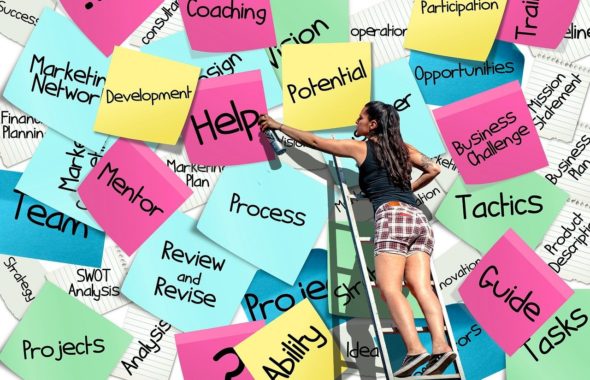
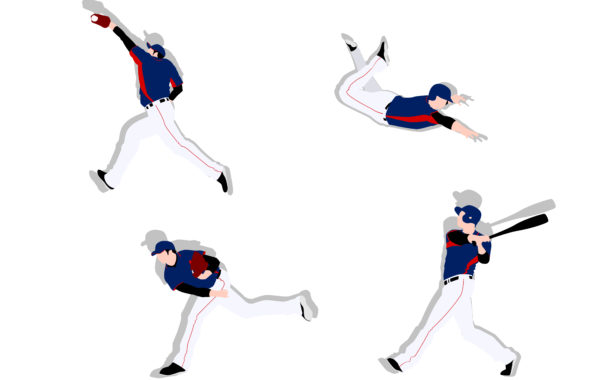

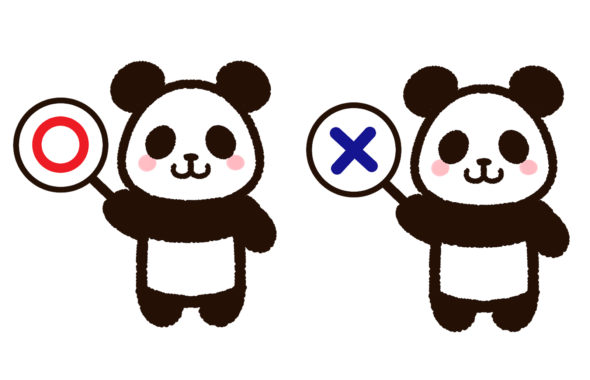
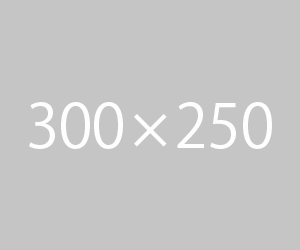
この記事へのコメントはありません。